�k��DMR�Ŏ��{����PCR�Z�~�i�[�̊T�v
�@2014�N9��24����25���ߑO�܂ł�1�����A�k����Ȋw��������14���̈�t�ƋZ�p���ɑ��āA�C���t���G���U�E�C���X�̃Q�m�����o�̃Z�~�i�[�����{���܂����B���̃Z�~�i�[�́A�t�]�ʃ|�������[�[�A������(RT-PCR)�ƈ�`�q�V�[�N�G���X�ɂ��C���t���G���U�E�C���X�����o�����{�I�ȋZ�p�ƒm�����w�Ԃ��Ƃ�ړI�Ƃ��čs���܂����BPCR�̃Z�~�i�[�́A�V�������Ƒ�w�@���̋ߓ����S�����A�V�[�G���X�Z�~�i�[�́A�c���搶�ƒ��J��搶���S�����܂����BPCR�̋Z�p�Z�~�i�[�ł́A�@�C���t���G���U�E�C���X��RNA���o�A�AcDNA�����A�B�R���x���V���i��PCR��p����A�^�C���t���G���U�̌��o�ƇCB�^�C���t���G���U�E�C���X�̌��o�̎��Z�w�������܂����B
9��24���ߑO�A�~�����}�[�ł́A�������w�ׂ�@����Ȃ��̂ŁA���߂Ď������������s���Q���҂��唼���߂Ă��܂����B���̂��߁A���߂Ƀs�y�b�g������@��������Ă���A�C���t���G���U�E�C���X��RNA���o�̎����Ɏ��|����܂����B2014�N7�������1�����ԁA�V����w���ەی��w�����Ŏ����g���[�j���O����Khin Moe Aung�搶�ɂ��T�|�[�g���Ă��炢�܂���(�ʐ^1)�BHaung Naw�����Thant Sin Win����\���āA12�T���v����RNA���o�����܂���(�ʐ^2)�B

�ʐ^1�@�~�[�e�B���O����Khin Moe Aung�搶(����)�ƃZ�~�i�[�Q����

�ʐ^2�@���o�̎������s���Ă���Hangnaw����
9��24���ߌ�A�ߑO���ɒ��o�����T���v����p����cDNA�̍������s���܂����B���������O�ɁA�m�[�g�փT���v������}�X�^�[mix�̋L�ڂ����Ă�����Ă����̂ŁA�����Ɏ������i�݂܂����B���̎����ł́A���ɁA�y�f�̎�舵���ɂ��Đ������A�N���b�V���A�C�X�̏�����Y��Ȃ��悤�ɓ`���܂����B
���̓��̍Ō�́APCR��p����A�^�C���t���G���U�̌��o���s���܂���(�ʐ^3)�B
���̎����ł́AA�^�C���t���G���U�E�C���X��M2��`�q���^�[�Q�b�g�ɂ��Ă��邱�ƁAPCR�̃X�e�b�v(1.�M�ϐ�, 2.�A�j�[�����O, 3.�L������)�ɂ��Đ��������܂����BPCR�̃������I������̂�17�����߂��Ă������߁A�Q���̍쐬�܂ōs���A���ʂ̊m�F�͗����ɂ��܂����B���̃Z�~�i�[�ł́A�g�p�������Ƃ��Ȃ����[�J�[�̋@��Ŏ������Ă������߁A������ƌ��ʂ��o�邩�ǂ��������S�z�ł����B�����͒x�����Ԃ܂ŃZ�~�i�[�����܂������A�Q���҂̏W������Ă��Ȃ��������Ƃɋ����܂���(�ʐ^4)�B

�ʐ^3 �g�p����PCR Thermal cycler

�ʐ^4 �����̎���(�d�C�j��)�Ɏg�p����o�b�t�@�[��������Haung Naw�����Thant Sin Win����
9��25���ߑO�A����s����PCR�̌��ʂ��m�F���܂����BA�^�C���t���G���U�̃o���h���m�F�ł��āA�����͐������Ă��܂���(�ʐ^5)�B����߂Ă����ْ����������a�炬�܂����B�m�F��́AB�^�C���t���G���U�����o���܂����B���̎����ł́AB�^��HA��`�q���^�[�Q�b�g�ɂ��Ă��邱�Ƃ�������܂����B�Ō�̎����ł́AHaung Naw�����Thant Sin Win����̃s�y�b�g��������S���Č��邱�Ƃ��ł��܂����BB�^�C���t���G���U�̃o���h���m�F�ł��APCR�Z�~�i�[�̎����͖����ɐ������ďI��邱�Ƃ��ł��܂����B�Z�~�i�[�Q���҂̕��Ɋ�{�I�ȋZ�p��`���邱�Ƃ��o�����Ǝv���܂��B
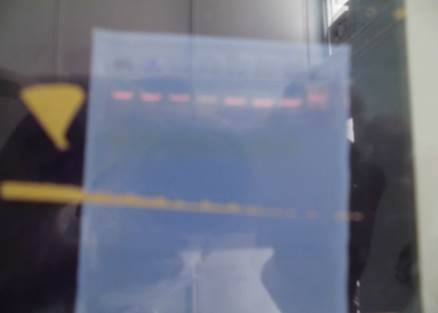
�ʐ^5 �@A�^�C���t���G���U��PCR�̌���
�Z�~�i�[�̏������T�|�[�g���Ē����܂������ەی��w�����̊F�l�ɂ́A��ϊ��ӂ������܂��B����̌o�������ɐ������Ċ撣�肽���Ǝv���܂��B
(2014.10.9 ���ӁF�ߓ���M)