新潟大学第三内科におけるPBC研究の歴史をめぐって
開講50周年を迎えるにあたり当科のPBC研究に関する歴史について上村朝輝 先生より御寄稿頂きました。
はじめに
昭和42年4月に新潟大学第三内科(現消化器内科)が開講し初代教授として市田文弘教授が就任されました。間もなく県内の病院から原因不明の黄疸例が次々に紹介され、当時は研究レベルであった抗ミトコンドリア抗体の検索により原発性胆汁性肝硬変(現在の原発性胆汁性胆管炎 PBC)であることが診断されました。これを契機に本症の研究は、その後に急速に進歩するウイルス肝炎の研究とともに教室のメインテーマとなっていったのです。
ここでは第三内科におけるPBC研究の歴史について、私の視点だけから紹介したものです。欠落している部分や研究に携わった方々が記載されていない場合があるかも知れませんがその点はご容赦ください。
なお、ここに記載された内容は研究の歴史であり、その後の進歩による現在のPBC研究とは別ではありますが、温故知新という見方でご覧いただければ幸いです。また、ここに記しました内容は第7回新潟PBC研究会(2011年6月23日)における講演内容を中心にしたものです。
PBC疾患概念の歴史
1892:Hanot “ Hypertroptic Cirrhosis ”
持続性進行性黄疸,肝脾腫,黄色腫,を呈する肝硬変
1948:Mac Mahon “Pericholangiolitic Biliary Cirrhosis”
皮膚掻痒感,黄疸,肝脾腫,高コレステロール血症,
病理組織学的所見:
門脈域周辺細胆管周囲炎
小葉間胆管の消失
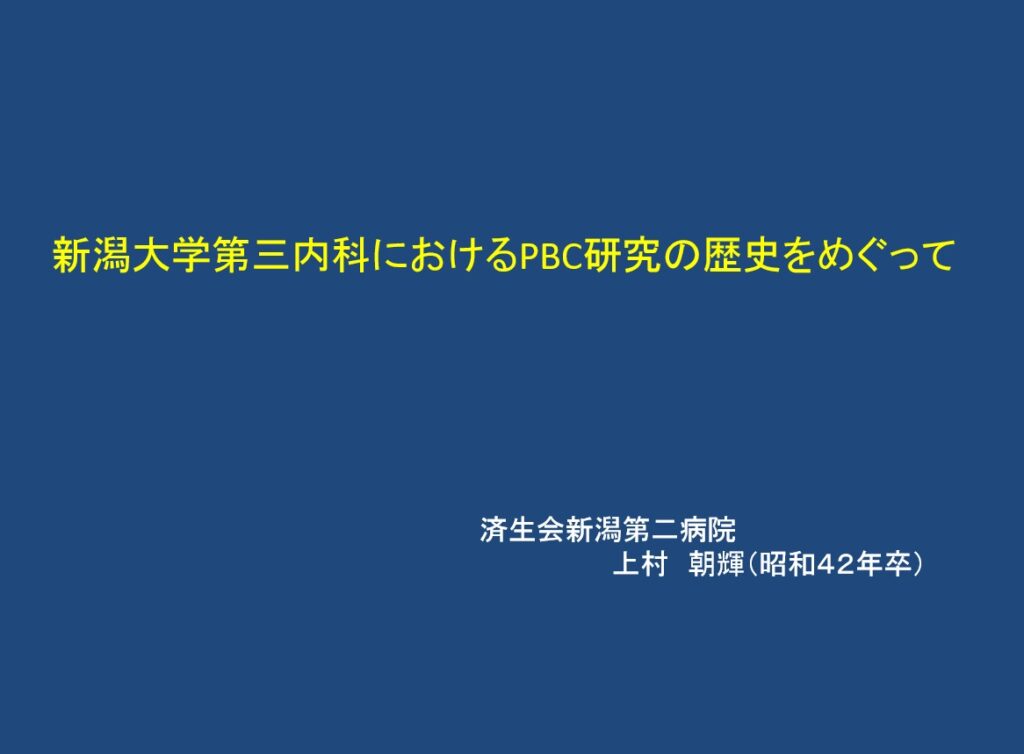
※全文はPDFファイルにてご覧いただけます。