
 |
麻酔科医の使命は、周術期の全身管理を行い、病気や手術侵襲からも患者を守ることです。麻酔科医は単なる麻酔薬投与係ではありません。周術期を中心とした急性期医療全般をカバーするのが麻酔科医です。麻酔科医としてキャリアを積んでいく上で、麻酔科研修の早い時期に麻酔管理、救急集中治療およびペインクリニック(緩和医療も含む)の全分野をできるだけ経験しておくことが重要です。気管挿管や静脈・動脈ライン確保、呼吸循環管理、体液管理(その他)は全ての臨床業務の基本です。手術麻酔によって得られた知識経験は救急集中治療の領域においても必ず役立ち、逆に救急集中治療で得られた経験は手術麻酔においても大きな自信となるでしょう。
|
| 教授 馬場 洋 |
また、ペインクリニック・緩和ケア研修を行うことによって、手術麻酔や救急医療における疼痛管理の幅が広がります。さらに外来治療、入院、手術、術後管理、退院、外来フォローという一連の流れの中で患者さんを見ることができるようになります。約10年後、自身のサブスペシャリティを持った後も、それ以外の分野について常に興味と関心を失わず、必要があればそれぞれのスペシャリストと密にコミュニケーションがとれるような人材を作っていきたいと思います。ただし、どの分野に進んでも麻酔科医としての基本を忘れず、常に軸足は手術麻酔においておくことが重要と考えています。平成21年秋には高次救命救急センターが開設される予定です(現在工事中)。それを支える手術室や集中治療部への期待も高まっています。当然、麻酔科への期待も高まっています。
一方、当科には基礎研究室にも負けないくらいの研究設備が整っています。パッチクランプ法や細胞内記録法を中心とした痛み・脳脊髄虚血・麻酔メカニズムの電気生理学的研究が盛んです。また、誘発電位等を用いた臨床での電気生理学的研究や経食道エコーを用いた循環管理の研究も行っています。良い臨床医は良い研究者にもなれます。逆は必ずしも正しくないと思います。臨床・研究・教育をバランス良くできるような人材を育成していきたいと思っています。
以上、堅苦しいことばかり述べてきましたが、要は楽しく夢のある仕事ができ、同時に教室員やその家族が幸せになれるような教室を作りたいと思っています。科長になってから7〜8年が過ぎ、40歳台半ばの年齢になってしまいましたが、当科はまだまだ発展途上にある若い教室です。若い力を待っています。
麻酔科医の仕事は患者様の生活の質(Quality of life)に深く関わる仕事です。医療に質が問われるこの時代、麻酔科医の果たす社会的役割も確実に大きくなっていきます。やりがいのある仕事ということができると思います。
欧米と比較するまでもなく麻酔科医の数は不足しています。特に東日本では著明で、新潟県全域でも麻酔科医の常勤する病院は20余しかありません。麻酔科医が常勤する病院であっても人員が足りていると言える施設はなく増員待ちの状態です。医師過剰と言われるこの時代にあっても麻酔科医のニーズは当分尽きることはありません。必要とされる人材、それが麻酔科医です。
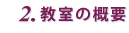
 【開講まで】
【開講まで】
1959年、当時は外科学教室にいらした一柳邦男先生が5年間の米国留学(ワシントン大学、L.E.
Morris教授の下、麻酔学研修)を終え帰国し、外科学教室講師に着任、学生講義(当時、麻酔学は外科学総論の中に包含)を担当、また臨床では外科学教室内の麻酔班の指導、そして、麻酔研究に従事されていました。
【開講以後】
 1963年、麻酔学教室発足、1964年 一柳邦男先生が初代教授として就任、1970年にはペインクリニック開設、1972年に一柳邦男先生が新設山形大学医学部附属病院長/山形大学麻酔学教室教授就任、しばらくの間、新潟大学麻酔学教室教授との併任をされました。
1974年、第二代目教授として下地恒毅先生が就任、1976年に麻酔外来(術前患者外来受診制度)を開始し、1991年には集中治療部開設しました。
2001年、下地教授定年退官後、第三代目教授として馬場洋先生が就任し現在に至っています。新潟大学医歯学総合病院には現在12の手術室があり、年間麻酔科管理症例数は約4,500件となっています。また近年手術室の移転を計画しており、手術室は14室に増える予定です。
1963年、麻酔学教室発足、1964年 一柳邦男先生が初代教授として就任、1970年にはペインクリニック開設、1972年に一柳邦男先生が新設山形大学医学部附属病院長/山形大学麻酔学教室教授就任、しばらくの間、新潟大学麻酔学教室教授との併任をされました。
1974年、第二代目教授として下地恒毅先生が就任、1976年に麻酔外来(術前患者外来受診制度)を開始し、1991年には集中治療部開設しました。
2001年、下地教授定年退官後、第三代目教授として馬場洋先生が就任し現在に至っています。新潟大学医歯学総合病院には現在12の手術室があり、年間麻酔科管理症例数は約4,500件となっています。また近年手術室の移転を計画しており、手術室は14室に増える予定です。

