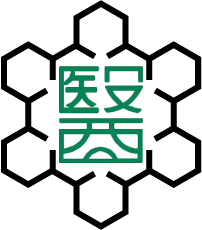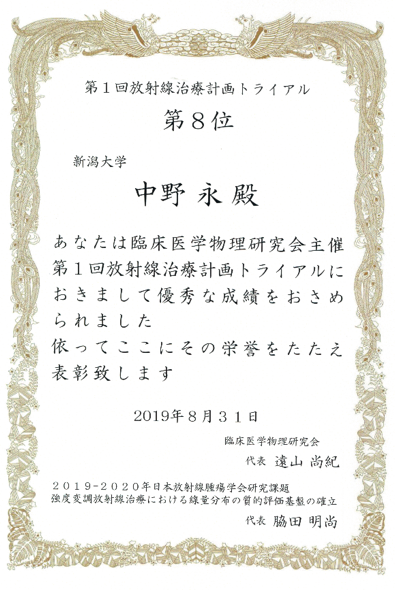|
 |
|
2019/11/23
|
|
 日本放射線腫瘍学会第32回学術大会(2019.11.21〜11.23 名古屋) 日本放射線腫瘍学会第32回学術大会(2019.11.21〜11.23 名古屋)
|
|
去る2019年11月21日〜23日の3日間、名古屋国際会議場に於いて日本放射線腫瘍学会第31回学術大会が開催されました。大会期間中は「切らずに治すがん治療-現時点での集大成と将来展望-」というテーマに相応しく、X線や粒子線、BNCTさらには免疫放射線療法など、様々なモダリティの発表が行われていました。
本学医学物理グループからは、棚邊が口演発表と教育講演(物理部門)、島津製作所共催ランチョンセミナー、滝澤さんはCyberknifeに関してポスター発表を行いました。また、大学院生の坂井まどかさんはradiomicsと機械学習を用いたIMRT QAに関して、共同研究者である魚沼基幹病院の桑原さんはSyncTraXFX4システムを用いた頭部領域の位置照合における被曝線量と位置精度を考慮した撮像条件の臨床的妥当性についてそれぞれ口演発表されました。
今年、新潟県内ではCyberknife(新潟脳外科病院)、Tomotherapy(長岡中央総合病院)による放射線治療が始まりました。各施設の新規立ち上げサポートをさせていただく中で、様々な関連病院と一緒に研究する土壌が年々整ってきたように感じています。日々の研究の成果が患者さんの治療成績の向上に寄与することを願いつつ、今後もグループ一丸となって努めていきたいと思います(棚邊哲史)

名古屋国際会議場の外観と中庭に面して立つ騎馬像(幻のスフォルツァ騎馬像))
|
|
|
 |
|
2019/9/30
|
|
 第1回放射線治療計画トライアル (2019-2020 JASTRO 研究課題)参加報告 第1回放射線治療計画トライアル (2019-2020 JASTRO 研究課題)参加報告
|
|
医学物理士レジデントの中野です。
2019-2020 JASTRO 研究課題 (強度変調放射線治療における線量分布の質的評価基盤の確立)の第1回放射線治療計画トライアルに参加し、全体で第8位(210人中)、治療計画装置 Eclipse (Varian社)部門において2位(121人中)の成績をおさめることができました。
放射線治療において強度変調放射線治療(IMRT)は周囲の正常組織に当たる放射線を最小限に抑えながら、腫瘍のみに放射線を集中して照射できるため、様々な部位に対して非常に有効な照射方法です。IMRT 治療計画では常に状況に応じて変化しうる理想的な線量分布を理解し、線量分布を自由自在に調整する技術と能力が必要だと考えられます。今回のトライアルでは理想的な線量分布に対して簡単には達成が困難な線量制約が与えられ、立案した治療計画を与えられた線量制約により点数化が行われました。したがって、より高い点数を取得できる計画者は線量分布を調整する能力が高い計画者と評価されるものでした。このトライアルにより自分自身の現在のIMRT 治療計画立案の能力を定量的かつ客観的に評価することができた有益なものでした。今回のような成績をおさめることができたのもIMRT 治療計画に関して日々指導をして下さる青山先生、宇都宮先生、棚邊先生、医学物理グループの皆様、そして新潟大学医学物理士レジデントコースの充実した教育体制によるものだと考えられます。
今回の結果に慢心することなく、今後とも臨床において求められる理想的な線量分布を作成するために必要な知識や技術の獲得に精進し続け、臨床に少しでも貢献できればと考えています (中野 永)。
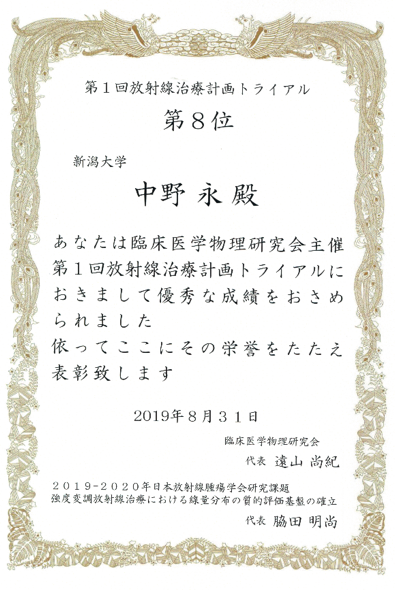
表彰状
|
|
|
 |
|
2019/9/3
|
|
 JSMP医学物理サマーセミナー2019 JSMP医学物理サマーセミナー2019
|
|
初めまして、新潟大学医学部保健学科放射線技術科学専攻4年の石坂夏希と申します。
新潟県のニューグリーンピア津南にて、2019年8月30日〜9月1日にJSMP医学物理サマーセミナーが行われました。
サマーセミナーでは、講義の開始時に講師の方々が理解の到達目標を示してから講義を開始します。このことにより自身の既知の知識の整理、新知識の吸収がスムーズに進みました。私は特に古徳先生による機械学習の講義が印象に残っています。これまで触れたことのない分野で数式全てを理解することは難しかったものの、今後の研究に幅を持たせる可能性を見出すことができました。
また、参加者のうち女性は私を含めて2人しかおらず、小澤先生は女性の参加者をもっと増やしたいとの考えがあるようです。一緒に過ごさせていただいた女性の医学物理士さんより「まだ女性の物理士が少なく周りにもなかなかいない」と聞きました。日々臨床業務に励む女性医学物理士さんのお話を聞いたことによって、私も医学物理士を目指し勉学に励むモチベーションが向上し、自分の人生についても考えるきっかけになりました。
今回のサマーセミナーで得られたことを今後の卒業研究や勉強に活かしていきます。

青山先生のご講義

ニューグリーンピア津南
|
|
|
 |
|
2019/8/2
|
|
 AAPM2019 参加報告 AAPM2019 参加報告
|
|
新潟大学大学院保健学研究科博士前期課程2年の坂井まどかと申します。
2019年7月14日から19日に、アメリカのテキサス州サンアントニオで開催されたAAPM 2019の参加報告をさせて頂きます。
新潟大学からは私と宇都宮先生と棚邊先生の3名が参加しました。
私にとっては初めてのアメリカ合衆国、初めての国際学会でした。そこで、“Machine Learning with Radiomic Features to Detect the Types of Errors in IMRT Patient-Specific QA”という題目で口頭発表を行いました。実は経由地のニューヨークで航空券の発券トラブルに見舞われ、サンアントニオ着が一日遅れてしまい、あわや発表見送り、となるところでしたが、周囲の先生方のご尽力のおかげで無事に発表を終えることができ、感謝の気持ちでいっぱいです。
AAPMでは、どの分野の発表においてもDeep learning や機械学習が当たり前のように用いられており、いまやこれらAI関連の知識は必須であるように感じました。また、日本からも著名な医学物理士の先生方や、自分と同年代の学生の方が多く参加されており、たくさん有益な情報を得ることができました。
私個人として非常に印象に残ったこととして、女性の研究者がとても多く発表されていたことが挙げられます。日本の医学物理学会はあまり女性が多くないので、同じ分野で活躍されている先輩方の姿にはとても勇気づけられました。
修士在学中に、国際学会で発表する機会を得られたことは、自分にとって大きな自信になりましたし、何より今後の研究活動や医学物理士を目指す大きなモチベーションとなりました。
修士も残すところあと半年程となりましたが、研究の精度をより上げていきたいと思います。

口頭発表の様子

他大学の医学物理士の先生方とRiver walkにて
|
|
|
 |
|
2019/5/7
|
|
 Practical Radiation Oncology (PRO) 誌に基礎配属実習の研究成果の論文が掲載されました Practical Radiation Oncology (PRO) 誌に基礎配属実習の研究成果の論文が掲載されました
|
|
以前、放射線治療科に基礎配属実習で来て頂いていた医学科学生(当時)の山本潤さん(2016年度)、薩摩有葉さん(2015年度)、大石まゆさん(2014年度)の一連の研究成果をまとめた論文が、この度Practical Radiation Oncology (PRO) 誌に掲載されましたのでご報告いたします(下記にリンク先からダウンロード可能です)。これは、前立腺がんの放射線治療におけるIMRTの導入とIGRTの導入によるPTVマージンの縮小が直腸有害事象発生率低減の観点からみて相補的な関係にあることを定量的に示した研究です。学生の方々に毎年少しづつ研究成果を積み上げて頂いた成果を最終的に英語論文の形にまとめることができたことは大変嬉しいですし、改めて3名の学生の方に感謝申し上げたいと思います。私個人的には、データの一つ一つには大きな新規性は認め難いとしても、研究方針を明確に定めて粘り強くデータを集めればレベルの高い研究として成立しうるということをあらためて実感できましたし、結果的に上記の3名の学生の方々にそのことを教えていただけたようにも感じています。
Utsunomiya S, Yamamoto J, Tanabe S, Oishi M, Satsuma A, Kaidu M, Abe E, Ohta A, Kushima N, Aoyama H: Complementary Relation Between the Improvement of Dose Delivery Technique and PTV Margin Reduction in Dose-Escalated Radiation Therapy for Prostate Cancer. Pract Radiat Oncol 9(3):172-178,2019
https:// www.practicalradonc.org/ article/ S1879-8500(19)30048-7/ fulltext
(文責 宇都宮悟)
|
|
|
|
 |