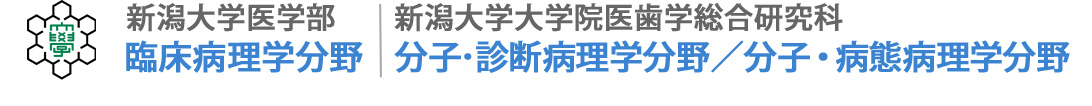Youはどうして臨床病理へ?
『そういえば病理のことあまり知らないなあ・・・。』
『病理医もありかも・・・?』
『病理ってどんな感じなのかな?』
初期臨床研修中、いや、もしかしたら学生のときに、
ふと「病理」が頭をよぎったあなた、または現在進行形で検討中のあなたへ、
ベールに包まれている(?)「病理」について、
現在当教室に在籍している先生たちに、
「なぜここにいるのか?」
「病理学教室はどんなところなのか?」
などなど、生の声を聞きました。
第4回 渡邉 佳緒里先生の場合
学部卒業と同時に結婚し、初期研修中の出産を機に病理へ進むことを決める。現在は2児の母となり、仕事と育児の両立に奮闘中。

-病理に進もうと決めたのはいつでしたか?
初期研修が終了するときです。学生のときは体全体をみることができる分野に進みたいと考えていました。関節リウマチや全身性エリテマトーデス(SLE)などの免疫を扱う膠原病内科に興味があったので、初期研修は第2内科コースを選択していました。
そのとき既に結婚していたのですが、初期研修の1年目に妊娠がわかり、出産のために6ヶ月休みました。その後の子育てを考えたときに、このまま内科に行くのはかなり厳しいと感じました。内科も実際にはいろいろな働き方があるのだろうと思いますが、自分の性格も考えて、病理を選びました。
子供のときからどのような仕組みで体は動くのかとか、自分では見えない「自分の鼻」に迷いなく指を持っていけるはどうしてだろうとか、本当に不思議で面白くて、高校時代には理系志望の友達とそのような話をして盛り上がっていました。医学部に入ったことも、元々仕事としての医療者にあこがれていたわけではなく、生命や病気の仕組みや成り立ちについて学びたいと思ったからです。だから学部4年生の基礎配属のときは病理を選び、当教室でお世話になりました。子どもが生まれたことは病理を選んだ大きな理由の一つですが、学生のときに病理に触れていたので、選択肢の一つには入っていました。
-臨床科と病理は子育て環境の面から考えるとかなり違いますか?
そうですね。私は大学病院の病理部にも所属していますが、病理は夜中に呼ばれない、時間に縛られないことが大きなメリットです。臨床だと外来があれば朝の7時半頃に出勤することもありますし、カンファレンスが夜の7時や8時から始まることもあります。それらは自分の都合で時間を変えることはできません。私も夫も県外出身者なので、子どもの面倒をみてくれる人が周りにいる状況ではなく、臨床に進むのは厳しいと思いました。子供を持つ医師にとって病理に進むメリットは大きいと思います。限りある時間を子育てと仕事とで分けることになるので、自由度が高い方がより効率的に動けます。子育てに限らず、仕事とそれ以外の何かも頑張りたいという人に、病理は特に向いていると思います。
-ご出身は県外ということですが、新潟市は住みやすいですか?
はい、新潟市は信濃川沿いにやすらぎ堤という広い緑地がありますし、郊外にも大きな公園があり,都市施設も充実していて住みやすい街だと思います。家から信濃川まで歩いて行けるので、よく子ども達とやすらぎ堤を散歩しています。
-病理のどのような部分を面白いと感じますか?
病理で組織と向き合うようになって、細胞は私が想像していたよりも遥かに自由に形を変えるものだとわかり驚きました。学生や研修生のときは細胞をじっくりみる機会がほとんどなかったので、細胞についてほとんど理解していませんでした。人間の体の中では、細胞は細胞でそれぞれが個々に生きて活動しています。また同じ病気だとしても、細胞は全く同じように変化しているわけではなく、一人ひとりにおいて違います。私達の意思が細胞を制御しているわけではなく、細胞は細胞で世界をつくっていて、本当に面白いと思います。
臨床では患者さんの症状を通して病気と向き合うので、病気そのものをみることはできません。けれども病理医は直接病気を目でみています。作業は顕微鏡で組織標本をみるというシンプルなものですが、とても具体的です。
残念ながら病理標本はある一瞬を切り取ったものなので時間経過は追えませんが、病態生理を自分の目で実際にみることができることが病理の面白いところです。
-仕事と子育ての両立で悩んだ時期もありましたか?
そうですね。子育て中だからと言って、教室の当番を特に減らされているわけではありません。それは私にとってありがたいことですが、与えられている仕事は何とかこなしているけど、それ以外のことがほとんどできなくて同僚に申し訳ない気持ちも正直あります。いろいろと悩むことはありますし、最初の子どものときは特に大変でした。
そんなときにフェイスブックCOOのシェリル・サンドバーグが書いた「LEAN IN (リーン・イン)女性、仕事、リーダーへの意欲」(日本経済新聞出版社)を読んで、こんな有名な人でもいろいろなことに悩んでいる事実にとても励まされました。その中でシェリルは人生や仕事をジャングルジムに例えています。登っていくルートは、はしごみたいな一直線である必要はなく、いろいろな方向からアプローチできるものなのだと、大変なことがあったら少しそれてみたり、粘ったりして、そこから降りてしまいさえしなければまた登っていけると言っています。仕事などに悩んでいる多くの女性に読んでもらいたい本です。
(インタビュー日 2016年4月22日)
インタビュー後記 聞き手 教室パート事務員 A子
佳緒里先生は華奢な方なので、最初子どもがいると聞いてとても驚いた。1人だと思っていたら、実は2人目だとわかり、また驚いた。いろいろと気が周り、とてもしっかりされている印象があるけど、高校生の頃の話をされているときは目がキラキラしていて、人間や体の不思議にワクワクし好奇心にあふれた理系女子が顔を覗かせた。また夫がとても協力的なのでやっていけるし、感謝していますという発言に、いまどきの夫はやはり協力的なのだと今の時代を実感した。前回の谷先生も育児にとても協力的だった。
新潟大学医学部 臨床病理学分野は人材募集中です!見学を希望される医学部学生さんや研修医の先生は、総括医長の高村佳緒里までお気軽にご連絡ください。025-227-2096/メール takamura@med.niigata-u.ac.jp)