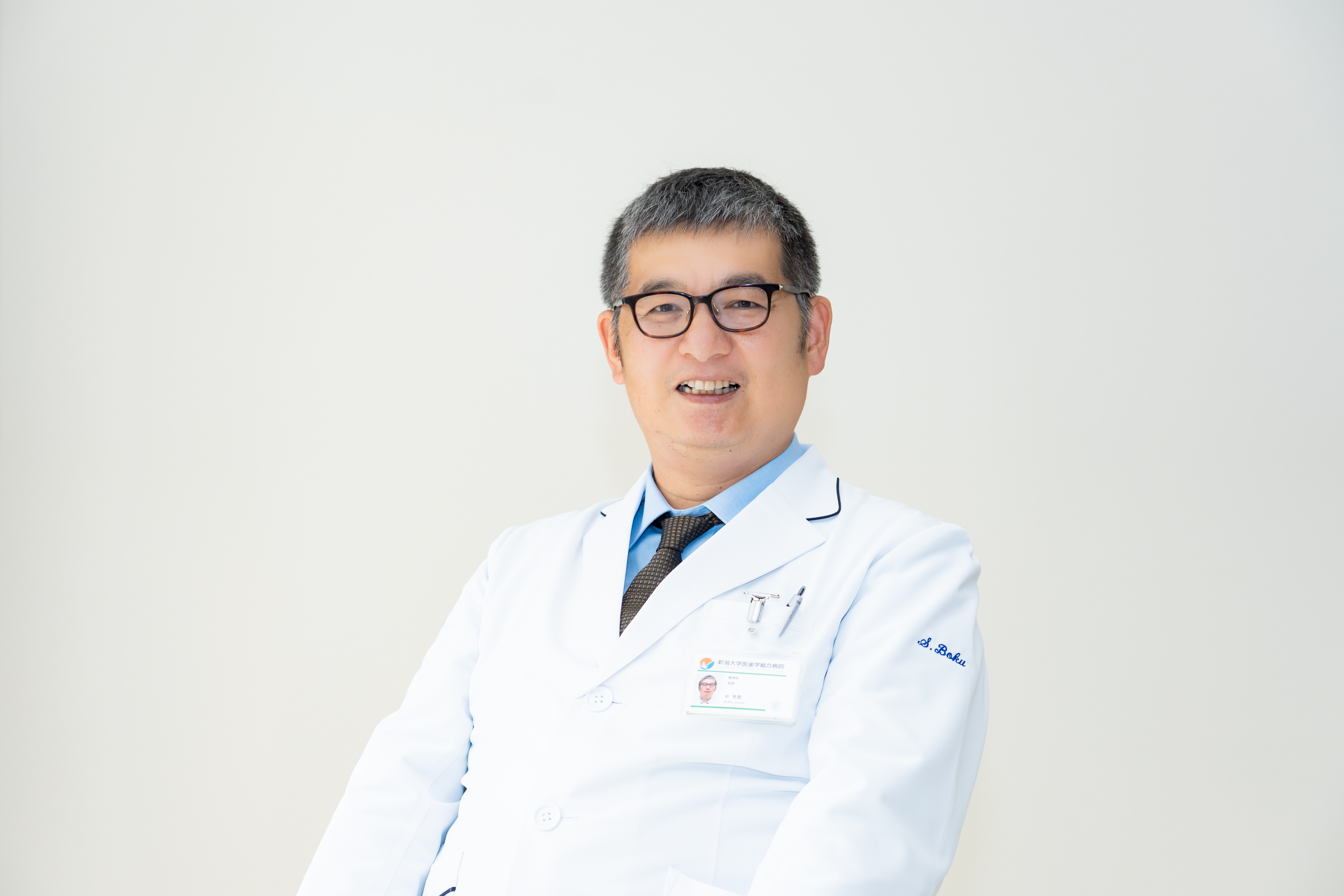
経歴:1998年3月 京都大学医学部 卒業
1998年4月〜2002年3月 京都大学大学院医学研究科博士課程(神経・細胞薬理学教室) 大学院生
1999年7月〜2001年3月 マックス・プランク分子生理学研究所 客員研究員
2002年4月〜2006年3月 北海道大学病院精神科神経科
2006年4月〜2012年6月 北海道大学病院精神科神経科 医員〜助教
2012年7月〜2014年8月 アルバート・アインシュタイン医科大学 博士研究員
2014年9月〜2019年10月 神戸大学 講師
2019年11月〜2025年3月 熊本大学 准教授
2025年4月〜現在 新潟大学大学院医歯学総合研究科精神医学分野 教授
2025年5月〜現在 熊本大学 客員教授
資格:博士(医学)、精神保健指定医、精神保健判定医、精神科専門医・指定医、一般連携精神医学専門医・指導医、精神科薬物療法専門医、産業医
学会役職:評議員(日本生物学的精神医学会、日本神経精神薬理学会、日本うつ病学会、日本不安症学会)、日本総合病院精神医学会ECT委員会委員、 臨床TMS研究会世話人、米国神経精神薬理学会(ACNP) Associate Member
専門:気分障害、依存症、ニューロモデュレーション、司法精神医学、神経細胞新生・アストロサイトに着目した精神疾患の基礎研究

経歴:新潟大学、2003年入局、2018~2020年マイアミ大学神経外科に研究留学
資格:医学博士(2012年)、精神保健指定医、日本精神神経学会認定専門医・指導医、子どものこころ専門医・指導医、日本小児精神神経学会認定医
所属学会:日本精神神経学会、日本生物学的精神医学会(評議員)、日本精神科診断学会(評議員)、日本小児精神神経学会、日本児童青年期精神医学会、日本EMDR学会
研究テーマ:自閉スペクトラム症の病態研究

専門:児童精神医学、
経歴:新潟大学卒、医学博士

専門:児童精神医学
経歴:福島県立医科大学卒

経歴:新潟大学卒、2016年入局、2025年同大学院修了
資格:医学博士(新潟大学大学院医歯学総合研究科生体機能調節医学専攻)、日本精神神経学会認定専門医・指導医、精神保健指定医、産業医、ワインエキスパート、第一種狩猟免許
所属学会:日本精神神経学会、日本神経科学学会、日本臨床精神薬理学会
研究テーマ:心の理論、抗精神病薬の副作用
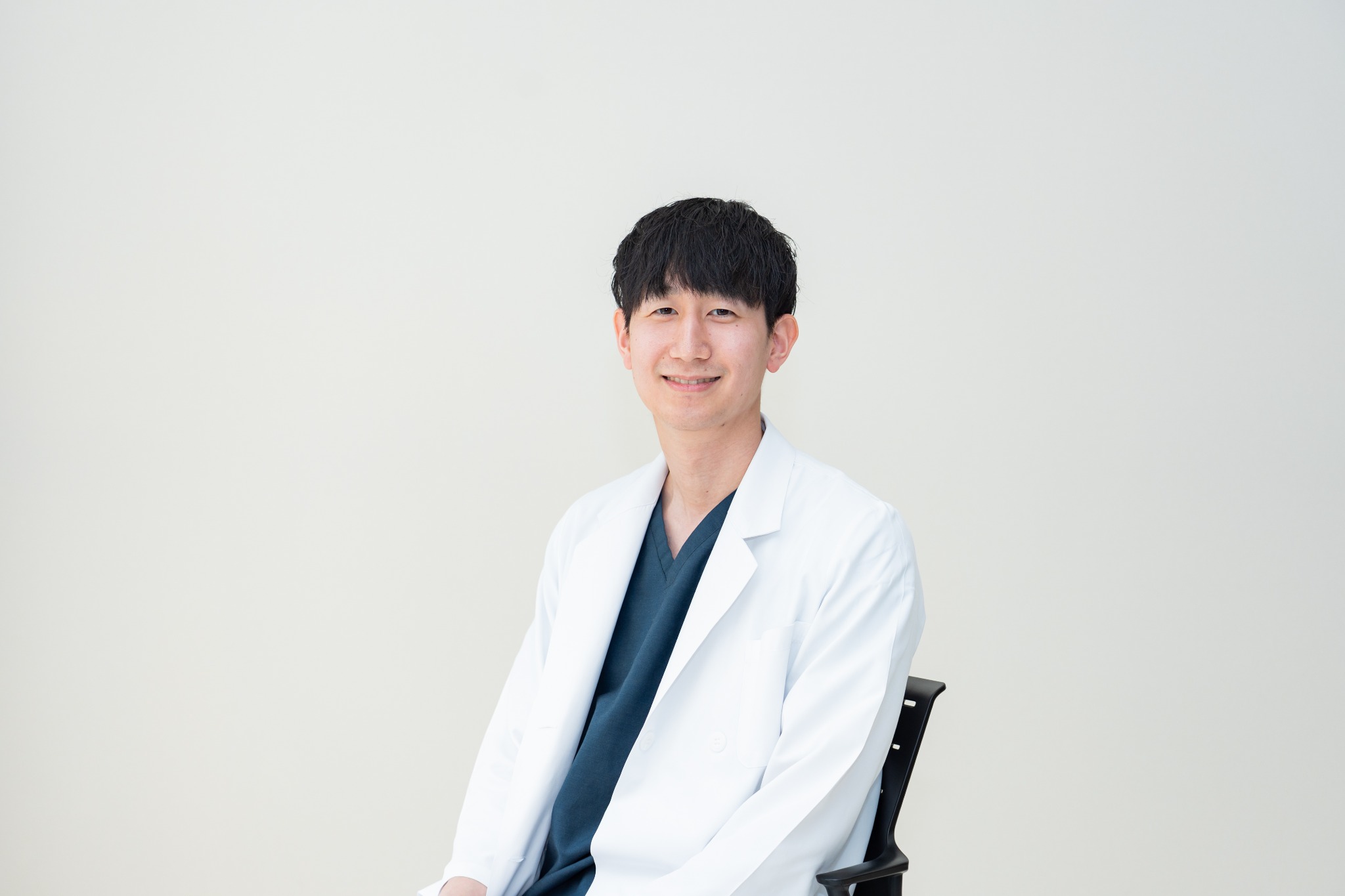
経歴:新潟大学卒、2020年入局
資格:日本精神神経学会認定専門医・指導医、精神保健指定医
所属学会:日本精神神経学会、日本精神科診断学会

経歴:Hasanuddin 大学(2011-2017)、新潟大学(2019-2023)、Ph.D. (2023)
資格:Medical Doctor
所属学会:Japanese Society of Biological Psychiatry; World Federation of Societies of Biological Psychiatry
研究テーマ:Neuromolecular genetics of Autism

経歴:2006年8月〜2011年10月 ハサヌディン大学 医学部 医学科
2016年1月〜2020年7月 ハサヌディン大学 医学部 精神科専門医課程
2018年10月〜11月 島根大学 医学部 精神医学教室 研究生
2021年4月〜2024年3月 新潟大学大学院 医歯学総合研究科 博士課程修了
資格:医師免許(インドネシア)2011年12月
マインドフルネス認定講師 2020年1月
精神科医免許(インドネシア)2020年11月
Certificate Program in Traumatic Stress Studies 修了(Trauma Research Foundation, 米国、2024年3月)
認定EMDRセラピスト(日本EMDR学会、2024年11月)
IFSレベル1認定セラピスト(IFS Institute, 米国、2025年6月)
所属学会:公益社団法人 日本精神神経学会(国際会員)、日本EMDR学会、Indonesian Psychiatric Association(インドネシア精神医学会)、Asian College of Neuropsychopharmacology(AsCNP)、Global Mental Health Think Tank、World Network of Psychiatric Trainees
研究テーマ:周産期の女性のメンタルヘルス、児童青年精神医学、いじめの予防と介入に関する国際共同研究(ICoRIPI)
経歴:2018年3月新潟大学卒業
2018年4月新潟医療センターで初期研修を開始
2020年4月新潟大学精神医学教室に入局
以降、新潟大学と新潟県立精神医療センターで、精神科・児童精神科として勤務
資格:精神科専門医、精神保健指定医、認定産業医
所属学会:日本精神神経学会、日本児童青年精神医学会
研究テーマ:発達障害、いじめ対策
新潟大学医歯学総合病院魚沼地域医療教育センター(略称:新潟大学地域医療教育センター)精神科は、魚沼地域医療再編に伴って2015年6月1日に開院した魚沼基幹病院と協力し、地域に根差した臨床、教育、研究を行っております。
臨床では、地域の皆様が最適な精神科医療を円滑に受けられるように関係機関と連携し、主に次の役割を果たしていきます。
地域医療や精神科専門医療を担う医師を育成することも私たちの重要な使命です。学生や初期・後期研修医には、診療チームの一員として、病院のスタッフや保健師、地域をよく知る方々とも協力して患者さんやそのご家族が抱える困難を理解し、さまざまな面でサポートする姿勢をもって医療に従事してほしいと考えています。そして研修医・学生が単科精神科病院では経験することが難しい治療場面に関われるように配慮し、総合病院精神科ならではのプログラムを充実させます。意欲ある多くの皆さんと一緒に実習や研修ができることを楽しみにしています。
臨床の場に接していると、現在の精神医学では解決されていない課題に直面することがあります。精神疾患の治療法の進歩は患者さんの回復に大きく貢献してきましたが、それでも未だ十分とは言えません。原因が未解明の精神疾患は依然として少なくはありませんが、脳機能解析や遺伝子解析などの進歩によって原因解明の糸口がつかめるのではないかと期待されています。臨床の現場で見出された課題を解決するために、新潟大学大学院医歯学総合研究科精神医学分野と協力して研究を行い、その成果を魚沼から国内外に発信していきます。
新潟大学地域医療教育センター精神科では、臨床・教育・研究を通じて地域の医療に貢献するとともに、国内外で活躍できる人材の育成に取り組んでまいります。皆様のご協力とご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
新潟大学地域精神医療学寄附講座は、新潟県からの寄附により2015年4月1日、新潟大学大学院医歯学総合研究科に設置された講座であり、県の精神科医療における新潟県立精神医療センター内にサテライト・オフィスを置き、同センターを中心に臨床、研究、教育において、次の役割を果たしています。
新潟県立精神医療センターは自体が拠点病院であって、その基本的役割は従来医療と先進的医療の併存提供にあります。具体的には、入院を前提とした従来型精神科社会復帰、地域移行支援の促進、精神科救急医療の充実など精神科基幹病院として必要な機能に加え、アルコールや薬物に関する依存症医療、災害時心のケアなどを行う災害精神医療、医療観察法病棟などの様々な取り組みを現場で担っています。
当寄附講座では、これらの多様な業務と密な連携を図るため、新潟大学大学院医歯学総合研究科精神医学分野、新潟県立精神医療センターと協力し、良質な精神科救急の提供、受療機会の平等化に向けた調査や診療、精神科専門医の育成を図ることで、新潟県の精神科医療への貢献を目指しています。
疫学研究の分野では精神疾患に特に統合失調症を患う患者の、平均寿命は一般人口よりも10~25年短いと報告されています。この差は「モータリティ・ギャップ」と呼ばれています。その背景には心血管系疾患が関係しており、患者さんの生命や健康に多大な影響が出ています。当寄附講座では、心血管系疾患の危険因子に関する調査や生活習慣改善について調査を進め、リスクファクターの介入、受診啓発、適切なモニタリングについて検討し、精神疾患治療モデルの確立を目指します。
治療抵抗性のケースは統合失調症の総患者数の約3割に達するとされ、自由域の一部である好中球が減少してしまう副作用が全体の約1%程度に出現するため、定期的な採血が条件で1~2週間に一度の通院が必要とされます。現在、県内においては対応施設が限られ、遠隔通院が課題とされています。当講座では、新潟県立精神医療センターと連携し、クロザピンをはじめとした治療抵抗性統合失調症に向けた診療と研究に取り組み、患者負担の軽減と治療機会の平等化を目指しています。
児童精神科領域はその診療特性・制度特性・研修体制等の観点から精神科一般の中でも専門性が特に高く、従事者は非常に限られています。
新潟県では近年、児童精神科医療の基盤整備が進みつつあり、例えば新潟県立精神医療センター内に開設された「子ども・思春期ユニット」では、広汎性発達障害、注意欠如多動性障害、摂食障害、心的外傷後ストレス障害など、多様な疾患に対応する新たな小児精神科医療の体制が整備されつつあります。
当寄附講座では、こうした新潟県内の実情を踏まえ、発達障害や不登校、虐待などに対応できる人材・多職種の育成や診療体制の確立を目指した研究活動を行ってまいります。