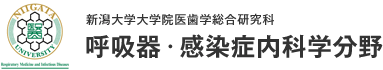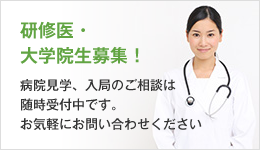びまん性呼吸器疾患研究グループ

間質性肺炎やサルコイドーシスなどのいわゆる「びまん性肺疾患」を研究対象としているグループです。びまん性肺疾患は、原因不明、続発性、腫瘍、感染症、稀な肺疾患など様々な疾患が含まれるため鑑別診断が難しく、たとえ診断がついたとしても治療法が確立していない疾患も少なくありません。このような多様なびまん性肺疾患の研究は、ヒトを対象とするのかマウスなどの動物モデルを対象とするのか、ヒトを対象とする場合どの疾患を対象とするか、対象疾患を決めた場合病態を明らかにするのか治療法を確立するのかなど、研究をはじめる前に考えなければいけない点が多くあります。また治療法が確立していない疾患でも症例は集まってきますので、そのような症例に対する治療方針は立てておく必要があります。われわれのグループの診療と研究の現状につき、ご紹介します。
研究について
1)電子線マイクロアナライザーを用いた吸入関連肺疾患の研究
従来電子線マイクロアナライザー(electron probe microanalyzer; EPMA)を用いて、吸入関連肺疾患の肺病理検体を対象に元素分析を行ってまいりました。寄せられた元素分析依頼は、それぞれ症例報告として和文、英文で報告されており、これらをまとめた英文総説も掲載されています。
分析依頼をご希望の方は、
- ご依頼者名(姓)/Last name
- ご依頼者名(名)/First name
- 病院・施設名/Hospital, Institution
- お住まい/Residence(都道府県/Country name)
- 所属/Department
- メールアドレス/Email address
- お問い合わせ内容/Inquiries
以上を記載の上、moriyama.hiroshi.wn@mail.hosp.go.jpまでご連絡ください。
2)参加している臨床研究
代表的なびまん性肺疾患である間質性肺炎は熟練した呼吸器内科医でも正確な診断が難しく、放射線診断医や病理診断医とともに検討するMDD:Multidisciplinary discussionが有用とされ、当院では主に外科的肺生検を施行された患者さんについて開催しておりますが、MDDを行える施設は全国的に限られています。この問題に対して、日本全国の間質性肺炎患者さんの病歴や検査結果を登録してオンラインでのMDDを行って診断を試みると同時に、その後の経過も集積することによって臨床アウトカム予測モデルを作成するPROMISE試験に参加しております。この試験で集積されたデータは、AIによる間質性肺炎診断アルゴリズムの開発を進めるIBiS試験にも用いられます。
間質性肺炎の中でも皮膚筋炎/多発性筋炎にともなうものは生命・機能予後が不良な難治性であるものから治療反応性・予後が良好なものまで極めて多様であり、的確な診療が困難な病気です。希少疾患であるため世界的にも十分なエビデンス・ガイドラインが不足しており、この病気の予後予測因子の解析を目的として患者さんの情報を集積するJAMI試験にも参加しております。
3)シロリムス新作用研究会
難治性稀少肺疾患であるリンパ脈管筋腫症(LAM)に対するシロリムスの薬剤承認に関連する治験に研究分担者として参加し、2014年7月に承認されましたが、シロリムスの新作用と応用に関して基礎研究・臨床研究の両面からアプローチするため、先進医療開拓部門の中田光特任教授とともにシロリムス新作用研究会(Japanese Association of Sirolimus Medical Investigation Network:ジャスミン研究会)を設立し、研究に取り組む研究者や臨床家への支援を行っております。