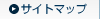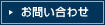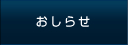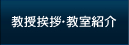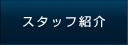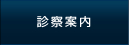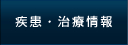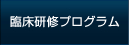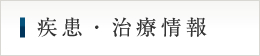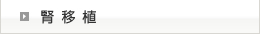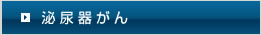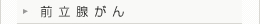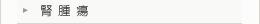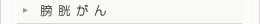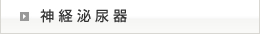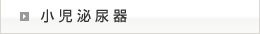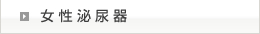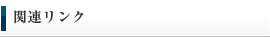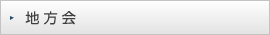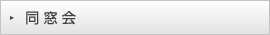HOME > 疾患・治療情報 > 泌尿器がん > 精巣がん
はじめに
精巣は、男性ホルモンを分泌し、精子をつくる男性生殖器で、ここに発生する悪性腫瘍が精巣がんで、ほとんどは精子を作る精母細胞から発生します。男性にのみ発生するがんで、その頻度は10万人あたり1〜2人ぐらいの割合で、好発年齢は、2歳以下の乳幼児期と20〜30代の青壮年期です。発生原因は、停留精巣や外傷との関係が指摘されていますが、必ずしも因果関係があるとは限りません。
精巣がんは、病理組織学的に下記のように分類されます。
(1) 精上皮腫
(2) 非精上皮腫 (胎児性がん、卵黄嚢腫瘍、絨毛上皮がん、奇形腫 )
精上皮腫では抗がん剤を投与する化学療法と放射線療法がともに有効ですが、非精上皮腫では化学療法は有効ですが、放射線療法は有効でないため、精上皮腫と非精上皮腫の分類は、その後の治療方針を決定する上で非常に重要です。
症状と診断
症状は、痛みや発熱を伴わない陰嚢内のしこりや精巣腫大です。痛みがないため放置すると高率に転移を起こし、転移病巣による症状で発見されることもあります。
腹部大動脈や大静脈の周囲のリンパ節に転移を起こすと腹部腫瘤として触れたり、腰痛を訴えるようになります。また、多数の肺転移を起こすと、咳や血液の混じった痰が出るようになります。
診断は、最初に陰嚢内の触診により腫瘤(しこり)を確認します。また、超音波検査で精巣内の様子を観察し診断することができます。組織型により、AFP、HCG、LDHなどの腫瘍マーカーが上昇しているものもあるため血液検査も行います。
精巣がんが疑われた場合には、このがんは非常に速く増殖し、転移しやすいという特徴がありますので、診断の意味も込めて直ちに精巣を摘出する手術をし、病理組織学的に確定診断を行います。
精巣がんの診断が確定したら、次に転移の有無に関する診断を行います。
多くの場合、最初に転移するのは腹部大動脈周囲のリンパ節で、精巣からリンパ管を経由して転移します。次いで肺やさらに肝臓、脳などに転移します。
腹部リンパ節転移や肝転移に対しては腹部CTや腹部超音波検査、ときにMRIなどが実施されます。肺転移に対しては、胸部単純撮影、胸部CTが実施されます。脳転移についてはMRIあるいは、脳CTが実施されます。
病期
転移の有無により病期の進み具合(病期)を以下のように分類します。
I期:
がんが精巣に限局している場合をいいます。実際には、原発病巣である精巣摘出後に、各種の転移を検索する検査で異常を認めず、かつ腫瘍マーカーの上昇があった場合には、この数値が精巣摘出後に順調に低下し、正常化した場合をI期としています。
II期:
横隔膜以下のリンパ節転移、つまり腹部大動脈、大静脈周囲のリンパ節だけに転移している状態をII期と定義しています。
III期:
転移が横隔膜以上のリンパ節にまで認められた場合をIIIa期、肺に認められた場合をIIIb期、さらに肝や脳転移が認められた場合をIIIc期としています。
各病期(ステージ)別治療
I期:
精巣摘出術にてほぼ完治しますので、通常はそのまま何もしないで観察します。しかし、1〜2割で再発や転移起こす場合があり、転移の出現を予防するための治療を追加することもあります。
II期、III期:
転移が一度確認された時には、すでに病気が全身に拡がっている可能性も考慮して、多くは抗がん剤による全身的化学療法が選択されます。現在ではシスプラチン、エトポシド、及びブレオマイシンの3剤併用(BEP療法)を1コース/3週間で施行することが初期化学療法として効果と副作用が確立され、一般的に第一選択となっています。化学療法後、腫瘍が残存した場合、手術による摘出や他の抗癌剤による二次化学療法も考慮されます。
精上皮腫では、放射線療法が有効であること、比較的に肺、肝、脳転移などの血行性転移が少ないことから、直径5cm以下の横隔膜以下の腹部リンパ節転移では放射線療法のみでも十分に根治が期待され、放射線療法のみで終了することも可能です。
治療の副作用
抗がん剤の副作用としては、食欲不振、嘔気・嘔吐などの消化器症状と、腎機能障害、耳鳴り、難聴、手指末端の知覚障害などの末梢神経障害、白血球数や血小板数の低下や脱毛などがあります。
この腎機能障害、末梢神経障害は永久に残ることがあります。しかし、副作用を軽減する処置を徹底することで、かなり予防することが可能です。
精上皮腫に対して実施される放射線療法では、現在その総照射量は多い量ではありませんので、腹部大血管周囲のリンパ節に照射した場合でも、副作用はあまり重篤ではありません。照射中の全身倦怠感、食思不振、下痢、微熱なども一時的なものです