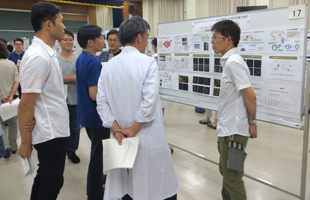1.研究概要
ウイルス学分野では、B型及びC型肝炎ウイルス、新型コロナウイルス、ならびに小児パレコウイルス感染症に対するウイルス学的な特性(感染・複製機構、病原性発症機構、自然免疫応答など)を明らかにする為の基礎研究を行なっています。また、それらの特性の理解から、ウイルス排除の方法論(抗ウイルス剤やワクチン開発、ゲノム編集技術の応用など)を開発することを目指しています。詳しい研究内容や業績については、ウイルス学分野のホームページを参照してください。
2.研究テーマ
2-1. B型及びC型肝炎ウイルスに対する病原性発症機序の解析
- HCV感染症に対する直接作用型の抗ウイルス剤の開発により、C型慢性肝炎が治療可能な時代になっています。その一方で、ウイルス排除後の肝疾患発症や薬剤耐性株の出現、またワクチン未開発のために再感染のリスクが存在するなどの問題点があります。私達はHCVの感染生活環の理解を通じて、その知見に立脚した治療法開発などの基礎研究を展開しています。また、B型肝炎ウイルスのウイルス学的性質の理解に関する研究や、創薬開発研究にも取り組んでいます。
2-2. 新型コロナウイルスによる自然免疫応答の回避機構の解析
- 2020年に発生した新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の世界的なパンデミックは、私達の生活や社会に大きな損害と変革をもたらしました。SARS-CoV-2が私達の社会に身近な存在となった可能性があることから、再びのパンデミックが懸念されます。私達はSARS-CoV-2の自然免疫回避機構や病原性発現機序の解明に取り組んでいます。
2-3. ウイルス感染を認識する細胞内自然免疫応答の解析
- 2011年のノーベル医学生理学賞は自然免疫研究が受賞対象でした。多様な微生物を認識するToll様受容体、RNAセンサー、DNAセンサー、ならびにインフラマソームなどの自然免疫応答は、微生物感染症の排除に寄与します。同時に、それらの機能不全や先天性の遺伝子変異は自己炎症性疾患の発症にもつながります。私達はウイルス感染に対する自然免疫応答の包括的理解を目指した研究に取り組んでいます。
2-4. 小児パレコウイルス感染症の病原性発症機序の解析
- 新潟大学医学部では、小児パレコウイルス感染症に対する基礎と臨床、ならびに疫学的な観点から包括的な国際共同研究を展開しています。具体的には、新潟大学医学部小児科学分野と新潟大学大学院保健学研究科の研究グループと共に、パレコウイルス感染の感染複製機構及び病原性発症機序の解明やワクチン及び抗ウイルス剤開発の為の基礎研究を行っています。
3.研究の成果
3-1. C型肝炎ウイルス感染によるタイトジャンクションバリアに対する干渉作用
- 細胞間タイトジャンクションのバリア機構は、細胞間隙の物質移動のみならずウイルス感染伝播の制御にも関与しており、その恒常性維持の破綻は肝疾患発症のみならず、多様な疾患の発症(難聴、癌の浸潤、アレルギー疾患、皮膚炎、炎症性腸疾患や糖尿病など)にも繋がる。しかしながら、タイトジャンクションバリアの恒常性維持の破綻に伴う肝疾患発症の分子機構は不明である。私達は最近、肝細胞におけるC型肝炎ウイルス(HCV)の感染伝播の促進に、タイトジャンクションバリア機構の破綻が関与していることを明らかにした(図1を参照)(Abe T, et al. J. Virol 2023)。興味深いことに、その影響は、DAA処理に伴うウイルス排除後にも持続することが示された。この様な観点から、HCV感染によるタイトジャンクションバリア機構破綻の不可逆的な持続とウイルス排除後に起こる肝疾患発症との関連性が推察され、この点についてさらに詳細な研究を行っている。
- 参考文献:Abe T, et al. Hepatitis C virus disrupts annexin 5-mediated occluding integrity through downregulation of protein kinase C-alpha and protein kinase C-eta expression, thereby promoting viral propagation. J Virol., 2023, e00655-23.

3-2. DNAを認識する細胞内自然免疫応答の包括的理解
- ウイルス由来のDNAゲノム(非自己DNA)や宿主のゲノムDNA成分(自己DNA)は、セカンドメッセンジャー合成酵素であるcGAS分子に認識され、シグナルアダプターであるSTING分子の活性化を介してインターフェロンが発現誘導される(図2を参照)。インターフェロンは抗ウイルス自然免疫応答として機能する一方で、その過剰な発現は「インターフェロノパシー」と呼ばれる自己炎症性疾患を誘発する。私達は、cGAS/STINGを介したシグナル経路の解析から、インターフェロノパシー疾患発症の分子機序解明に取り組んでいる。
- 参考文献:Abe T, et al. Cytosolic DNA-sensing immune response and viral infection. Microbiol Immunol., 2019, 63:51-64.

3-3. 新型コロナウイルス由来プロテアーゼによる自然免疫回避機構
- SARS-CoV-2の性状の中で、特に、宿主の抗ウイルス応答とウイルスによる逃避機構の分子機序には不明な点が多い。自然免疫誘導性のユビキチン様蛋白質修飾反応(ISG15化反応)は、様々なウイルス感染に対して主要な抗ウイルス応答として機能するが、その作用機序ならびにウイルスによる逃避機構はウイルス毎に多様であり、その包括的な分子機序は未だ明らかにされていない。私達は最近、SARS-CoV-2由来ヌクレオカプシド蛋白質が、ISG15化反応を介した抗ウイルス応答の標的であることを新たに見出した(図3を参照)(Rhamadianti AF, et al. J. Virol 2024)。同時に、ウイルス由来のパパイン様プロテアーゼ(PLpro)が、ヌクレオカプシド蛋白質のISG15化反応を阻害することが明らかとなった。
- 参考文献:Rhamadianti AF, et al. SARS-CoV-2 papain-like protease inhibits ISGylation of the viral nucleocapsid protein to evade host anti-viral immunity. J Virol., 2024, e00855-24.

3-4. パレコウイルス感染受容体の同定
- CRISPR gRNAライブラリを使用したゲノムワイドスクリーニングを用いて、ヒトパレコウイルスの感染受容体であるMYADM(Myeloid-associated differentiation marker)分子を同定した(Watanabe K, et al. Nat Commun 2023*)。現在、私達は、レポーター遺伝子発現組換えパレコウイルスや感染動物モデルを活用し、ウイルス病原性発症機序の解析や宿主自然免疫応答の回避機構の解明に取り組んでいる。*ウイルス学教室前任者の研究成果
- 参考文献:Watanabe K, et al. Myeloid-associated differentiation marker is an essential host factor for human parechovirus PeV-A3 entry. Nat Commun., 2023, 14:1817.