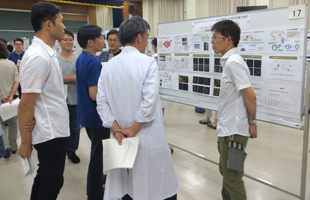慢性炎症の原因となるタンパク質を新たに特定 −ぜんそくなどの慢性炎症性疾患の新たな治療法開発に期待−
新潟大学大学院医歯学総合研究科の青木亜美助教が参加する研究グループは、「組織常在性記憶CD4+T細胞(CD4+TRM細胞)」)が肺や腸などの組織に長期間とどまるメカニズムと、炎症性サイトカインの持続的な産生は、遺伝子の働きを調節するタンパク質である転写因子Hepatic Leukemia Factor(HLF))によって制御されていることを新たに特定しました。
今回の成果は、ぜんそくや関節リウマチなどの疾患に見られる慢性炎症の発症の仕組みを分子レベルで解明したものであり、HLFを標的とした新しい治療法の開発につながる可能性が期待されます。
詳細はこちらをご覧ください。
慢性炎症の原因となるタンパク質を新たに特定 −ぜんそくなどの慢性炎症性疾患の新たな治療法開発に期待−(PDF)
本件に関するお問い合わせ先
広報事務室
E-mail:pr-office@adm.niigata-u.ac.jp