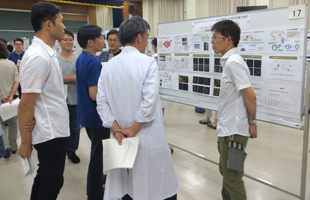リサイクル異常症という新たな疾患発症メカニズム −様々な合併症を伴う原因不明の小児難病の病態を解明−
新潟大学大学院医歯学総合研究科腎・膠原病内科学分野の斎藤亮彦特任教授が参加する研究グループは、これまで原因が不明であった小児難病において、新たな原因遺伝子を複数発見するとともに、患者さんに見られる様々な合併症の発症メカニズムを明らかにしました。
詳細はこちらをご覧ください。
リサイクル異常症という新たな疾患発症メカニズム −様々な合併症を伴う原因不明の小児難病の病態を解明−(PDF)
本件に関するお問い合わせ先
【研究に関すること】
新潟大学 大学院医歯学総合研究科 腎・膠原病内科学分野
特任教授 斎藤 亮彦(さいとうあきひこ)
E-mail:akisaito@med.niigata-u.ac.jp
【広報担当】
広報事務室
E-mail:pr-office@adm.niigata-u.ac.jp