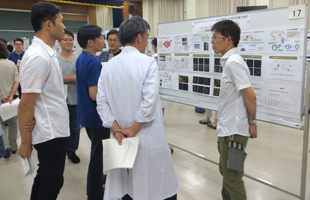HPVワクチンによる子宮頸部前がん病変予防効果を確認 −NIIGATA study:初交前接種でより高い予防効果−
本研究成果にかかる記事は,内容の正誤や適切性を調査中のため,閲覧を一時中止しています。
2023年5月31日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
本研究成果にかかる記事は,一部内容に誤りがあったため,掲載をとりやめました。
訂正記事は以下をご覧ください。
https://www.med.niigata-u.ac.jp/contents/info/news_topics/280_index.html
2024年12月23日